聖痕大戦 "ブレイド・オブ・アルカナ" アナザーストーリー
Another Stories of "Blade of Arcana" Extra ARMAGEDDON
第一章 凍てる戦争
33『前兆』
西方暦一〇六〇年四月一五日〈ウェルティスタント・ガウ〉/王国自由都市ケルバー/エステルランド神聖王国北部
シーラの日常は修道院での日課と地域への奉仕で埋まっている。
今日は〈ウェルティスタント・ガウ〉一帯での活動だ。
その名の通り、〈ウェルティスタント・ガウ〉はどちらかといえば新派の影響が強い区域であったが、彼女は頓着しなかった。困っている人を救うことに、新派も旧派もないというのが彼女の持論だった。
通りに差しかかったシーラは顔見知りの家族や子供と挨拶を交わし、時には相談事を受け、最近の様子や困っていることについて訊ねたりもした。
返事はすべて同じだった。
最近、どうも治安が悪い。若い者たちが不満ばかり述べている。食糧の配給ぐらいはしてくれてもいいのではないか……。
もちろん、彼女ではどうにもならないことばかりであった。彼女に出きるのは、修道院から支給された金殻をもって購入したわずかばかりの食糧を配ることと、救世母に対する祈りを捧げるぐらいであった。対する人々は一応の謝意を述べた。祈りが現実に変化を及ぼさないことは理解していても、それを罵倒するほどの精神状況ではないからだ。
その態度を見る限り、まだ本当の危機ではないと言えるかもしれない。
困窮極まる人々がまず捨て去るのは、他者への礼であるからだ。
シーラの祈りに何の反応もなくなった時、それこそが何事かの終わり――そして始まりであるのかもしれない。
最も〈ウェルティスタント・ガウ〉で危険な一画と呼ばれている通りに、彼女は差しかかった。本人はそのような事情を全く知らない。いや、知っていたとしてもここに来ただろう。悪い人でも、悪い人だからこそ救われるべきだと思っているからだ。それはシーラの美点であり欠点であった。
いかにも品の悪そうな酒場の前を通り掛かった時、中からの声が漏れ聞こえた。
「もうこのままでは駄目だ」
「今日の食事にすら事欠いている……お袋は死にかけているんだ」
「なぜバーマイスターは俺たちを助けてくれない」
「なぜこんなことになってしまったんだ」
「なぜ」
「誰も俺たちを救う気がないんだ」
「バーマイスターもきっとそうなんだ」
「畜生」
「状況を知らないのかもしれない」
「ならば教えてやればいい」
「そうだ」
「そうだ」
「そうだ!」
何を話し合っているのだろう、シーラは思った。もっと聞きたいとも思った。だが、いかな彼女でも一人でこの酒場に入るのは気が引けた。この場を離れることにする。
奉仕を終え、修道院に戻った。
宿舎の部屋で今日の出来事を日誌にまとめつつシーラは思い出す。
やはりあの会話は気にかかる。まるで一揆か何かの相談事みたいだ。いや、考え過ぎかもしれないけれど。でも、でも。
何事かの前兆であるように思えるのは、わたしの気のせいなのかしら?
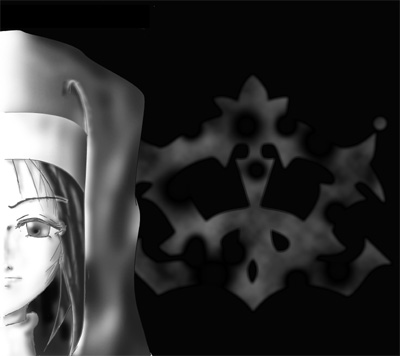
挿絵:2RI氏