聖痕大戦 "ブレイド・オブ・アルカナ" アナザーストーリー
Another Stories of "Blade of Arcana" Extra ARMAGEDDON
第一章 凍てる戦争
31『霊媒』
西方暦一〇六〇年四月一四日ケルバー南西部
傭兵大隊、歩兵第一大隊の訓練は、前日から実施されていた。その訓練内容は大きく分けて二つ、《雷の杖》射撃訓練と霊媒統制による調整攻撃訓練である。前者は歩兵第一大隊が、後者は傭兵大隊が主に行っている。十日間という限られた期間であるためか、常識をどこかに置き忘れたかのような日程でそれらは行われていた。大休止を兼ねた食事、仮眠を除けば常に血反吐を吐くような訓練を宛てがわれていた(日程の中には夜間襲撃訓練まで盛り込まれていた)。
頼りなげな朝日が辺りを照らす。濃い朝靄が立ちこめ、ぬるりと湿った、そしてまだ肌寒い空気が身体にまとわり付くようだ。貧弱な林に止まる鳥たちが囀っている。明るいとはいえないものの、平和な情景ではあった。
しかし、その情景は轟音に破られた。驚いた鳥たちが一斉に飛び立った。間を置いて再び轟音。罵り声。阿呆みたいに時間をかけやがって、それじゃ引き金を引く前に貴様らが挽肉にされているぞ――。
「あちらさんも気合を入れているようだね」
大隊本部天幕の中で傭兵大隊の訓練を始めようとしていたエアハルトが苦笑を交えつつ呟いた。轟音の原因――歩兵第一大隊が行う射撃訓練についての感想であった。
「バレルシュミット閣下は、十日以内に携行弾薬を使い切るつもりのようです」
レイガルが答えた。彼の背後には落ち込んだようにうなだれるリーフとティアが立ち尽くしている(実際落ち込んでいたのだが)。
彼女たちは到着したその日の夜に、傭兵隊に紛れ込んでいることがばれていた。理由はかなり間抜けたもので、寝床を確保できなかったせいだ。まさか傭兵隊の天幕に寝かせるわけにもいかず――貞操を危険にさらしたいなら別だが――、数少ない女性傭兵のための天幕は満杯。結果、困り果てたレイガルがエアハルトに相談したのであった。
結局彼女たちはエアハルト用の天幕を与えられ、エアハルト自身は大隊本部天幕で休むことになった。勢いで行動してろくなことはないという好例といえた。ちなみに落ち込んでいるのは、自分のわがままでエアハルトに迷惑をかけたことに対する自己嫌悪であるらしい。
「頼もしいことだ」
「訓練といえば、こちらも大したものだと思いますが」
レイガルの言葉には、どこか奇術を眺める観客にも似た響きがあった。彼の視線の先には、図台に置かれた地図に向けられている。周辺一帯の地形が書き込まれたそれには、二つの駒が配置されていた。
「大したものといえばそうかもしれない」
エアハルトが頷いた。苦笑いを浮かべる。
「なにしろ、戦場に立たずに部隊を操ろうというのだからね」
「なんというか、夢物語のようです」
「うん、妥当な表現だ」
エアハルトは頷いた。小さく溜息を吐く。閉め切ってもなお薄寒い天幕のせいか、薄い靄が口許に発生する。
「エアハルトさま」
いつもの平服ではなく、急いで仕立てられたダークブルーのケルバー軍軍装(野戦軍装)に身を包んだエミリアが天幕に入る。彼女は、天幕内にリーフとティアがいることに驚いたように目を見開いたが、すぐに視線をエアハルトに戻し、一礼した。彼女はすでにナインハルテン家の一員ではなく、“ケルバー防衛軍霊媒班”の指揮官として組織に組み入れられている(軍装の襟元には、大尉の階級が記されていた)がゆえの態度であった。
「準備が整いました」
「わかった。始めてくれ」
「はい」
エミリアが合図を送る。天幕内に二人の少女と、四人の兵が入り、図台を取り囲むように座った。
もう我慢できなかった。殊勝な態度をうっちゃって、リーフはこわごわとエアハルトに訊ねた。
「何をするの?」
「ちょっとした遊戯さ」
視線を向けずにエアハルトは答えた。目はエミリアたちに注がれている。まだ怒っているのかな、リーフは少ししょぼんとしながらうつむいた。
部下を監督しつつ、リーフの様子も窺っていたエミリアは、フォローするように口を開いた。
「霊媒による部隊の遠隔指揮、その訓練です」
「れーばい。えんかくしき?」
「戦場の後方にいながら、まるでその場にいるかのように部隊を操ることです」
レイガルが首を傾げるリーフに小さな声で教えた。
「……へー」
彼女は気のない返事をする。興味がないと言うより、そのことが何を意味しているのか理解できてないようだ。エアハルトは小さく笑って告げた。
「まあいいさ、見ていればわかる。ナインハルテン大尉、状況開始。第一、第二中隊に行動開始を下達」
「了解」
慣れぬ発音でエミリアは応じた(軍隊式のやり取りに一般人たる彼女が慣れているはずがない)。少女たちに頷く。少女たち――《サロン・フリーデン》の霊媒たち――は、まるで正真教信徒が礼拝をするように頭を垂れ、目を閉じた。祈念するかのようだ。
エアハルトが構想し、大隊首席参謀が作り上げた訓練計画は以下のようなものだった。
傭兵大隊麾下の三個中隊のうち、第三中隊を仮想敵として設定する。第三中隊は予め設定された野戦訓練区域内に前日のうちに移動している(第三中隊は区域内であれば自由に行動してよいことになっていた。つまり、敵状――どこに潜み、どう布陣するのかはまったく不明ということになる)。第一、第二中隊はその二四時間後に行動を開始する。
第一、第二中隊は基本的に大隊本部(この場合、エアハルト)の指揮下にあり、その行動は中隊本部に派遣された霊媒を通じて統制される(さらに、霊媒による思念索敵も状況に応じて用いられる)。
状況としては捜索撃滅戦と呼ばれるものだ。要約してしまえば敵を捜し求め、捕捉次第攻撃するということになる。ただ、その統制を後方司令部から行うというのが通常の野戦との大きな違いであった。
およそ一〇分ごとに、各中隊からの報告が霊媒を通じて大隊本部に送り込まれた。大隊本部に常駐する霊媒の声に従い、それに付いている兵が、中隊の位置を示す駒を動かしていく。思念索敵はまだ行ってはいない(エミリアの説明によれば、思念索敵は精神結合による連絡のやり取りに比べ精神の疲労度が大きく違うのだそうだ)。中隊の斥候班だけで索敵を行っていた。
図台を見詰めるエアハルトはまさしくチェスを行うように、霊媒を通じて部隊を動かした。通常の伝令による情報のやり取りでもこのような状況の管制は可能ではあるが、霊媒ならではの即時性(伝令到着までの時間浪費がない)が、部隊の統制をより容易にさせている。
「第二中隊より報告。前面八〇〇に敵兵を確認。恐らく斥候と認む」
「思念索敵を許可。第一中隊は座標点〇五―二四に東より接近せよ」
「了解。第二中隊に思念索敵を許可」
「了解。第一中隊は座標点〇五―二四へ東より接近させます」
エアハルトは第二中隊が動静を確認した地点に向けて、離れて索敵行動を行っていた第一中隊を移動させた。思念索敵により敵状が判明すれば、横合いから攻撃できる位置だ。
「第二中隊より報告。思念索敵により増強小隊規模の集団を確認せり」
「本部は後方か。第二中隊に攻撃命令。第一中隊は突撃隊形を組みつつ、〇五―二四をさらに旋回、北より攻撃を開始せよ」
「了解。第二中隊は攻撃開始、攻撃開始」
「了解。第一中隊は突撃隊形を組みつつ〇五―二四を旋回、北より襲撃せよ」
まるで彼自身が最前線の丘に陣取っているかのような指揮ぶりだった。
エアハルトは表面上では冷静な表情を保っていたが、内心では興奮を抑えきれなかった。
聞くのと実行するのでは大違いだな。後方――つまり、より大きな兵力を握る司令部が、前線の状況を逐一把握できるというのが、こんなに素晴らしいとは。混乱しがちな戦術状況を司令部で冷静に判断し、より大きな作戦状況に組み込む。素晴らしい。兵力の効率的運用。そう、まさに効率的。なるほど、聖救世軍が霊媒伝令網の構築を急ぐわけだ。そしてそれをケルバー軍に適用すると決断したエノアの決意も素晴らしい。これならば。これならば、ブレダの軍勢にも対処できるかもしれない。そう。効率的運用。効率的な殺人。なるほど。なるほど。
うっすらとエアハルトは微笑みを浮かべた。冷徹な野戦指揮官――大量殺戮に長けた者が浮かべるに相応しい表情だった。しかしそれはすぐに消えた。恐らく彼自身にはそんな表情をしていた自覚すらないだろう。
図台を注視するエミリア、レイガルにあれこれと質問を投げ付けるリーフはそれに気づかない。その表情を見たのは、常に彼だけを見詰めていたティアだけであった。
彼女は背筋に氷が触れたような感覚を覚えた。わずかに唇を噛みしめ、うつむく。
「第二中隊は敵前衛隊と接触。現在攻撃中」
「第一中隊、敵集団後方に占位。陣形再編が終了次第攻撃開始」
霊媒からの報告に、エアハルトは爽やかと形容すらできる声音で応えた。
「よろしい。第二中隊長に連絡。力攻せよ。第一中隊長にも連絡だ。再編急げ、蹂躙せよ」
後方での攻撃準備を気取られぬよう、第二中隊に正面からぶち当たれと命じているのであった。
一〇分後、突撃隊形を作り終えた第二中隊の後方からの襲撃により、第三中隊は揉み潰された。一対二の戦力比があるとはいえ一方的な戦果であった。
エアハルトは状況終了を宣言した。宿営地に戻るようにも命じる。まだ、今日の訓練が終わったわけではない。
夜。
宿営地のそこかしこで焚火がたかれ、それぞれ気の合う仲間同士で車座が形成されていた。喧騒が満ちている。食欲をそそるスープの匂い。くたびれ果てた兵たちが愚痴と雑談を交わしていた。
もちろん、兵どもが休憩していても指揮官には仕事がある。戦闘を表立って行わない代償といってもよい。
エアハルトは、燭台によって照らし出された大隊本部天幕内で書類仕事を行っていた。目を通していたのは、歩兵大隊の訓練で消費された弾薬算定量についての報告であった。空前の戦争が迫りつつあるケルバー軍は(とはいっても、それを知るのは軍上層部だけであったが)、兵站管理の面からも弾薬をおろそかには出来ない。正確に量を把握する必要があった。
「よー、エア〜」
天幕の外から、発音の怪しげな声がした。エアハルトは苦笑を浮かべた。声の主が誰であるのか、すぐにわかったからだ。
「入っていいよ、カリエッテ」
「おい〜す」
天幕に入ってきたのは、何とも隆々とした体躯の女性だった。頭が天幕の天辺に届きそうだ。しかし、その体格のバランスは実によく保たれている。つまり骨格からして人間のものではなかった。何より、額から突き出た二本の角が、自分が何者であるかを宣言している。彼女は鬼人族であった。
彼女の容貌は燭台の赤黒い照明でも判別できるほどの赤ら顔だ。かなり酩酊しているらしい。
「人付き合い悪いなぁ、エア。あんたも宴会に加わればいいのに」
酒杯を手に、カリエッテは笑った。その種の表情を浮かべると彼女は驚くほど幼い印象を与える。
「僕はこれでも大隊長なんだ。つまらない書類仕事も棒給のうちさ」
「僕、か……ほんとに変わったねぇ」
カリエッテは嘆息した。酒臭い息を嗅いで、エアハルトはわずかに顔をしかめる。
「色々あった。あの頃とは違う」
彼は微笑んだ。カリエッテは照れたように頬を武骨な指で掻いた。彼女の知るエアハルトは“戦鬼”の二つ名で呼ばれた、残虐で冷酷でどうしようもない悪辣な――だからこそ戦友として信用できる――男のはずであった。とても目の前の男と同一人物とは思えない(とはいえ、悪い変貌ではないことは彼女も認めていた。好ましい変化ともいえた)。
「……君から見て、どうだい? 他のみんなは」
仕事に対する集中力を削がれたため、気分転換をすることに決めたエアハルトは話題を切り替えた。羽根ペンを放り、懐から細巻を取り出す。
「あー……ケルバーだけあって、傭兵の質は悪くないな」
カリエッテは一息で酒杯を空けてから、答えた。ふん、と鼻を慣らし、大声で外に呼びかける。「誰か酒、酒持ってきてくれ!」
エアハルトは苦笑いを浮かべながら、燭台に顔を近付け細巻に火を付けた。燻らせる。外見と違い、彼女はひどく人懐っこい。もう部隊に友人というか遣い走りというか――ともかく、気の置けない仲間を得ているようだ。昔とまったく変わらないな。そういえば、亡霊狩猟団で僕に率先して話し掛けるような変人は、彼女ぐらいだったし……。
「ただ、やっぱりまだ集団で殴り込みをかけるのはなあ。今日の訓練でも、昔みたいにうまくはいかねえよ」
つまり新造の部隊ゆえに、調整の取れた行動が取れないということか。亡霊狩猟団のような、統一の取れた動きには不可能ということだな。エアハルトは紫煙を吹き出しながら彼女の言葉を翻訳した。
まあ仕方ないさ。ある程度までは訓練で鍛え上げ(だからこそ無茶苦茶な訓練日程を組んでいる)、あとは実戦で揉むしかない。エアハルトはそう判断している。訓練未了が生み出す無駄な戦死者は、計画上折り込み済みだ。もちろんそれを可能な限り減らすことが指揮官の務めであることもわかっている。
「でもまあ、あたしから見て筋のある奴は何人かいるよ」
「へえ」
エアハルトは先を促すように頷いた。彼自身も、傭兵採用の面接の際に、何人か見込みのある(指揮官として、見込みのある)者を何人か確認していた。その裏付けを聞きたかった。
「例えば……」
「し、失礼します!」
カリエッテの言葉を遮るように、慌てたような声が外から響く。エアハルトは入れ、と告げた。入口の遮幕をくぐり、少年が入る。いかにも重そうな瓶を抱えていた。
「おう、ザッシュか。悪いな」
カリエッテは瓶を受け取り、笑った。エアハルトは、ザッシュと呼ばれた少年を見遣った。なんとも頼りなげな風体だった。少年とも少女とも取れるような儚げな顔つきと、傭兵というにはあまりにも華奢な身体つき。珍しいことに青氷色と深紅色の瞳を持っている。そして、その瞳だけが全体の印象を裏切っている。確かに風体は頼りない。しかし目だけは、決断力に溢れた将軍のようだ。
エアハルトの視線に気づいたザッシュは、緊張したように直立不動の姿勢を取った。
「楽にしていい」
「はい、大隊長殿!」
返事はしたものの、姿勢は崩さない。当然かもしれない。彼は、目の前の男がどんな人間であるかをカリエッテから聞いていた。それに、熟練した傭兵が放つどこか冷たく乾いた雰囲気に気圧されてもいる。
エアハルトは苦笑を浮かべた。
「エア、こいつもその一人だぜ?」
「ふん?」
エアハルトは立ち上がり、人務参謀の机に置かれている書類をめくった。
「君、名前は?」
「ザシュフォード・クルス・クリスフォードです」
見つけた。エアハルトは自分の席に戻りつつ人務書類を目で追う。
ザシュフォード・クルス・クリスフォード。年齢一六。男。二年前から傭兵として活動。年齢の割には剣技に優れ、兵術にも理解がある(人務参謀は、名前、立ち振る舞い、教養などから考えて貴族か資産家の子弟ではないかと書き込んでいる)。なるほど、つまりは天性の資質だけでこれまで生きてきたということか。経験を積めば精兵となれるかもしれない。うん、特に兵術の理解がある点が素晴らしい。年齢さえ気にしなければ、部隊指揮官に抜擢していたかもしれない。
エアハルトは、カリエッテが筋があると言った訳を理解した。
「なるほど」
「な? それに性格もいいし、弟みたいな奴なんだ」
「カ、カリエッテさん……」
照れたようにザシュフォードは口ごもる。しかしそれはエアハルトの言葉によって凍り付いた。
「性格がいいかどうかは、戦いに関係ない」
根元まで吸いきった細巻を火壷に放り投げつつ、素っ気無く彼は告げた。
「いや、性格が出来ている奴ほど戦場では苦労する。クリスフォード君、覚えておけ。戦いで生き残るのは、常にろくでもないやつだ」
「……はい」
答えはしたが、ザシュフォードはどこか納得してない表情を浮かべている。
「理解できないのも当然だよ。こればかりは、戦場に立ち、生き残らないとわからない。だから今はそれでいい。でも、僕の言葉を覚えていてくれればありがたい」
「わかりました」
「下がってよろしい」
「失礼します」
ザシュフォードは天幕を退出した。カリエッテは小さく呟いた。
「わざわざ印象を悪くすることもないだろう」
「僕を慕って戦死されるより、嫌悪してても生き残ったほうがましだ。それに、僕は嘘を教えたわけじゃない」
「そうだけどさ」
「君も覚えているだろう? 戦場での僕がどれだけろくでなしだったか。今でもそうだ。それだけは変わらない。変わらないようにしている。でないと生き残れない」
いいや、変わったよ、あんたは。カリエッテは理解できない苛立ちを覚えつつ、内心で呟いた。昔のあんたなら、わざわざこんな忠告はしない。それだけでもえらい変化さ。
歌が終わった。やんややんやの喝采を浴びつつ、リーフは一礼した。
彼女は持ち前の明るさで、早くも傭兵たちの間で人気を構築し始めている。あちらこちらの車座に呼ばれ、歌をねだられてもいた。この座で三つ目だ。さすがに少し疲れ始めている。
リーフはなぜか宴会に付き合わされている(というより、リーフが引きずり廻しているのだが)ティアの隣に座った。もとよりティアは表情を出さない方だが、今は浮かない顔をしている。
「どしたの、ティア」
傭兵の一人から渡された酒杯を一息で空けた後、リーフは訊ねた。ぽつりとティアは答えた。
「……ここに来た理由、忘れてはいませんか」
「――――――そんなわけないじゃない」
ひどく間を空けて、リーフは答えた。ティアはあえて追究はしなかった。
「……エア、仕事中みたいなんだもの。邪魔できないわ」
視線を離れた所にある天幕に向ける。隙間から明かりが漏れていた。
リーフの横顔はどこか寂しげだった。そこで始めて、ティアはこれまでの彼女のはしゃいだ雰囲気が演技であったことに気づいた。
演習同行に気づいた昨夜から、確かにエアハルトは任務を理由に彼女たちを避けるようにしている(側にいることは時たま許しても、ほとんど会話を交わすことはなかった)。任務――業務、仕事――で忙しいのは事実かもしれない。しかし彼女たちには、エアハルトがそれを口実にしているように思えてならなかった。
もしかしたら、とティアは心の中で思った。マスターは本当にわたしやリーフさんと接したくないのかもしれない。脳裏に、演習の際に彼が浮かべた冷たく空虚な笑みが浮かぶ。今度の戦争において、マスターに望まれているのは優秀な部隊指揮官としての役割。そして優秀な指揮官とは、極論してしまえば人殺しの手管に長けた者のことだ。そしてマスターは、そう在ろうとしている。まさに周囲の人々に望むままに。それが“闇”への進軍だと知りつつも。そして変わっていく自分をわたしたちに見られたくないと思っているのかもしれない。なんてことなのだろう。
ティアは胸の奥を締めつけられるような感覚を覚えた。冗談ではない。叶うなら、すべてをかなぐり捨ててマスターとともにここから離れたいとすら思う。もちろんそれが無理なことはわかっている。悲劇が迫りつつあるケルバーの人々をマスターが見捨てることなどありえない。それが“防人”というものだから。なんという皮肉。つまりマスターを追い込んでいるのは“防人”の掟。そして“防人”として生きることを強要するわたしの存在。ならば、わたしがいなくなればいいのだろうか。わたしがマスターから離れればいいのだろうか。
そこまで思考を進めた途端、胸の奥の感覚が痛みへと変わった。きゅっと、胸元の法衣を指が白くなるほど握り締める。
嫌。それだけは絶対に嫌。マスターのそばから離れたくない。マスターから離れることなんて、絶対に出来ない。
ティアにとって、エアハルトという男はもはや“マスター”という言葉だけで括ることのできない対象であった。己に課せられた使命すら投げ打ってでもともに生きたいと思う存在であった。それは彼女にとって久しぶりの――もしかしたら初めての――人間であった。
彼女は、彼とともに生きてきた五年間という時の間に、彼をそう思うように自らを作り替えたのだ。
「――ティア。……ティア!?」
顔を上げる。心配そうにこちらを窺うリーフの顔が視界に入った。
「……なんですか、リーフさん」
「どうしたの? 急に押し黙ったりして。それに、なんかすごく思い詰めたような顔をしてたよ?」
「なんでもありません」
ティアがそう応えると、リーフはほんの少し怒ったような表情を浮かべた。「そういうの、そっくりね、エアに」
「え?」
「あたしが心配すると、いっつも“なんでもない”って」
リーフは怒ったまま、視線を焚火へと向けた。ティアは意外そうな顔をして、彼女の横顔を見詰める。
「わかってないよ、あなたもエアも。苦しそうな、困ったような顔をして、それでいて“なんでもない”なんて。誰だって嘘ってわかる。もっと心配しちゃうじゃない、そんなこと言われたら……」
「――すいません」
「いや、謝らなくてもいいけど、ね」
小さくリーフは笑う。「あ〜あ、エアももうちょっと素直になってくれればなぁ」
まるで母か姉のような口ぶりだった。
「……あなたたちは、大隊長の知り合い?」
「ぅわっ!?」
唐突に隣から声を掛けられたリーフは、大げさに驚いた。隣に座っていたのは、いかにも怪しげな仮面をかぶった女性だ。どうして今の今まで気づかなかったのだろうと、リーフは思った。
「……あ、あなたは?」
「リー。《星》小隊所属」
リーと名乗った女性は、仮面から覗く目でリーフを柔らかく見遣った。彼女の隣には、森人の少女が女性の肩に寄り添うようにうとうとと眠っている。リーフは、その少女に見覚えがあった。一カ月ほど前、傭兵募集の時に見掛けた記憶がある。
「なんですか、いきなり」
「大隊長の知り合いなの? あの、柔らかそうな顔つきをした人の」
柔らかそうな顔というのはエアのことかしら、リーフは脳裏にふにゃふにゃと笑うエアハルトを想像した。うん、確かに柔らかそうだ。
「エアのこと? ええ、そうよ。あたしの連れ」
なぜか偉そうにリーフは答えた。えっへんとでも言いたげに胸を反らす。頬が赤い。酒のせいだろう。
「連れ、ね。そう」
声音は笑いにも似た響きを伴っていたものの、リーの顔はけして笑ってはいない。
「それがなに? 聞いてどうするの?」
「……覚悟しておいた方がいいわ、あなた」
「?? 覚悟? なんのこと?――それと、あたしはリーフ・ニルムーンよ」
リーは向き直った。焚火の赤黒い炎を受けて半面だけが闇から浮き上がったその仮面は、まるで絵物語で語られる死神のようにも見える。そしてそこから覗く瞳は、ただ哀しみ――そして憐愍だけが満ちていた。
「リーフ・ニルムーン。あなたの連れ……エアハルト・フォン・ヴァハトは……遠からず死ぬことになるから」
どこまでも乾いた声で、リーは告げた。
薪が爆ぜる音。傭兵たちの談笑。辺りに満ちるのはそれだけだった。リーフはぽかんと仮面の女を見詰めていた。リーが何を言ったのかまったく理解できなかったからだ。もちろん小さな声であったとはいえ、彼女はリーの言葉を聞き取っている。しかし頭は、それを何か意味のあるものだと認識しなかった。
「何をおっしゃっているのですか、あなたは」
反論は意外な所から出た。小さくはあったが、語気は強い。ティアであった。
「わかってるわ、自分が何を言っているのか。何を意味しているのか。残念だけどね」
「……」
「そしてたぶん、あなたには心当たりがある。だからこそすぐに反応した。違う?」
リーは、反論した少女の姿に見覚えがあった。従者か何かだったはずだ。
ティアはただ、その整った顔に怒りにも似た感情を貼り付けてリーを睨み続けた。
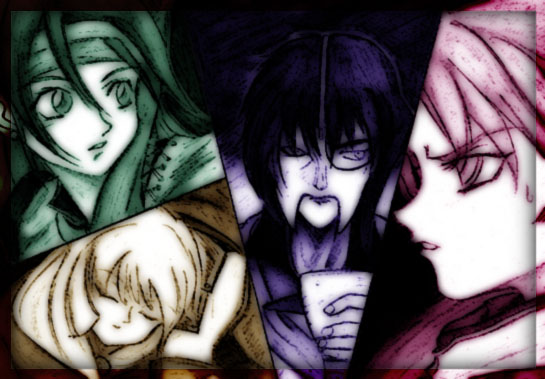
挿絵:孝さん
「もちろんろくなことじゃないことはわかってる。でも、何も知らされずにその時が訪れるよりましだと思わない?」
「……そりゃ、傭兵さんだから……戦争が近いから……戦えば、死ぬかもしれないけど……」
リーフがようやく、何かを理解したように呟いた。とりとめもない思考がそのままこぼれているかのようだ。視線が泳いでいる。
「でも……だからって……エアが死ぬわけじゃないもの」
「――後悔しないように、彼と接しておきなさい」
リーはまったく躊躇のない声音で告げた。「その方がいいわ」